チームを作るにはストッパーの役割が必要。シニア世代こそ適任かも
公開日 2022年11月12日
更新日 2023年12月 5日

こんにちは
ようこそいらっしゃいました
今日の本はこちらです
夏川草介著 レッドゾーン
チームには、ネガティブ思考とユーモアセンスの持ち主が必要

皆さんは、グループ活動しますか?
会社だけでなく、町内会やマンションの役員会、趣味の集まりなど・・
シニア世代、グループ活動する機会はたくさんありますよね。

PTAは、卒業したのにな
グループには必ずいる面倒な存在
そんな中で、
「ちょっと、あの人なんとかならないかしら?」
なんて存在いませんか?
せっかく決めたのに、ネガティブ発言をする人
ダジャレばかりの人・・
特に物事に真剣に取り組む人には、「ちっ!」と思うことも多々あるでしょう。

なんだか報われない気分
になりますよね
さて、物語はコロナ患者に向き合うチーム。
何もわからない状況で命に向き合うのですから、
真剣に一致団結して、意見を一つにして取り組まなければいけない
・・はずですが、
皮肉屋、ネガティブ、ダジャレという名のユーモアで乱す医師がいます。
なぜ、そんな人がこんな真剣な場所に選ばれたのでしょう。
違う意見の持ち主の存在が危険回避に導く
「コロナ診療は、使命感だけで突き進むには危険すぎる現場です。確実にブレーキをかけてくれる先生のような存在が必要だと考えました。危険なものは危険だと、突き進むことだけが正しいわけではないということを、はっきり言えるのは先生だけだと思ったのです。」
(レッドゾーン)
つまり、この未知の医療は、情熱だけで突き進んだら、共倒れする。
だからこそ、誰にも忖度せずに、思ったことをサラッと言える人が必要だったのです。
同じ意見を持っている人が良い人という発想ほど、危ないものはない
ということですね。

同調圧力なんて
持っての他ね!
危険が伴うときは、必ずストッパーの役割を果たせる人を入れること
自分の意見に反論する人を嫌い!なんていうのは言語道断。
嫌なこと言うな・・と思う前に、
この人は、自分にとってストッパーの役割を果たしているのではないか考えること
1度は、その意見にきちんと耳を傾ける習慣をきちんとつけなければいけない
ようです。

自分が取り返しのつかないことを
しないためにね。
さて、物語の医師は、存分にユーモアを交えながら、この役割を全うしていきます。
事情を知らない人には、なかなかヘビーな存在ですが・・

頭が下がります
でも、ただ和を乱す人では、この役割は果たせません。
実力も伴い、人間性も素晴らしい人であること
嫌われる勇気があること
・・最大の条件かもしれませんね。

こんな役割こそ
シニアの役割かもね
本について
著者 夏川草介 出版社 小学館
発行日 2022年8月23日
お父ちゃんはお医者さんなのに、
コロナの人、助けてあげなくていいの?コロナ禍の最前線に立つ現役医師(作家)が、
(レッドゾーン 小学館特設サイトより)
自らの経験をもとに綴った、勇気の記録!
『レッドゾーン』とは
防護服なしでの立ち入りが禁止されたコロナ患者が入院している領域のことです
物語は、令和2年2月。
長野県の呼吸器内科医も感染症医もいない地域病院『信濃山病院』
公立病院であるがために、新型コロナ患者の受け入れを決めたところから始まります。

コロナ禍
医師の皆さんの体験は壮絶です

よく乗り越えましたよね
色んな立場の人の状況を
知るのも大事
先に『臨床の砦』という作品が出版されていますが、『レッドゾーン』より数ヶ月後の話です。
どちらを先に読むかはお好みで!
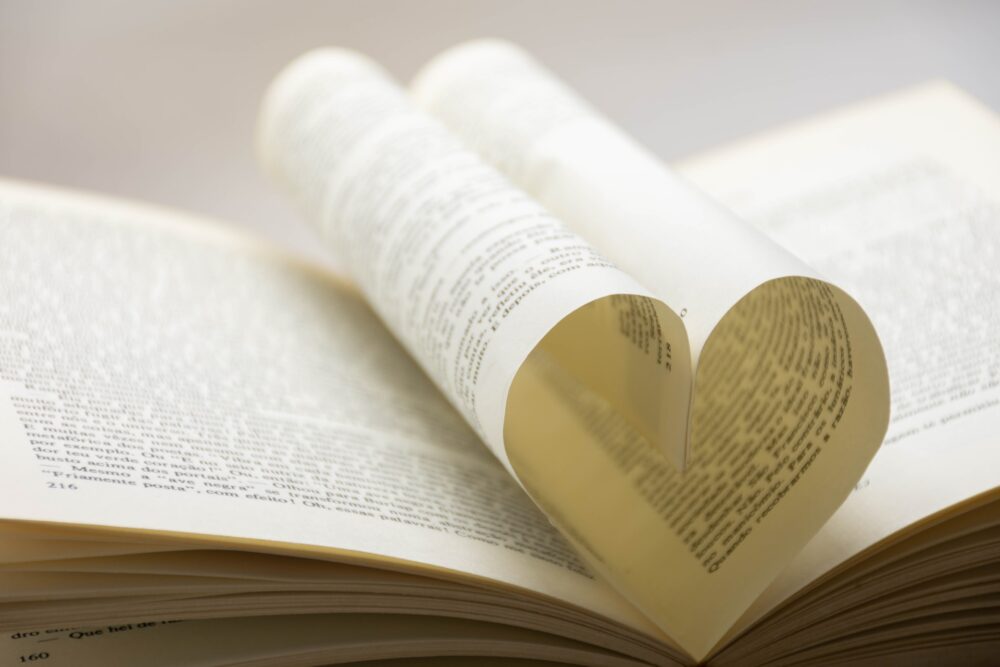


コメント